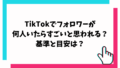春になるとスーパーで見かける「うすいえんどう」。
関西を中心に親しまれている豆ですが、
「グリンピースと何が違うの?」
「皮は食べられるの?」
と疑問に思う方も多いはずです。
実は、
うすいえんどうの皮は硬いため
基本的には食べられず、
中の豆だけを調理するのが一般的です。
とはいえ、
最近は皮を工夫して
スープなどに活用する方法もあり、
使い方次第で無駄なく楽しめるのも魅力です。
この記事では、
うすいえんどうの特徴や
グリンピースとの違い、
皮の剥き方のコツ、
さらに代表的な食べ方やレシピまで
わかりやすく解説します。
読み終えたときには、
うすいえんどうを
もっと気軽においしく
調理できるようになるはずです。
うすいえんどうとは?グリンピースとの違いを簡単に解説
春の味覚として親しまれている「うすいえんどう」。
一見すると
グリンピースやスナップえんどうと似ていますが、
実はそれぞれに特徴があり、
料理での使い方も少し違います。
ここでは、
うすいえんどうがどんな豆なのか、
そしてグリンピースとの違いを整理してみましょう。
うすいえんどうの基本情報と旬の時期
うすいえんどうは、
えんどう豆の一種で、
関西地方を中心に春の食卓に登場する定番食材です。
豆の粒がふっくらとしていて、
ほのかな甘みと優しい香りが特徴です。
毎年春先に出回る季節限定の豆として、
炊き込みご飯などに使われることが多いのも魅力ですね。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| うすいえんどう | ふっくらとした粒、甘みが強い、春が旬 |
| グリンピース | やや青みのある風味、幅広い料理に使われる |
| スナップえんどう | さやごと食べられる、シャキシャキ食感 |
グリンピース・スナップえんどうとの違い
グリンピースは
うすいえんどうに比べて香りが強く、
煮物や炒め物など幅広い料理に活用されています。
スナップえんどうはさらに別物で、
さやごと食べられるため
サラダや炒め物にぴったりです。
うすいえんどうは皮を食べず、
中の豆だけを楽しむのが基本なので、
ここが大きな違いといえるでしょう。
似ているようで少しずつ役割が異なるので、
料理に合わせて使い分けると楽しみが広がります。
うすいえんどうの皮は食べられる?
「うすいえんどうの皮って食べられるの?」
と疑問に思う方は少なくありません。
見た目がスナップえんどうに似ているため、
さやごと食べられるのでは
と考えてしまうのも自然ですよね。
ここでは、
皮の食べられる部分と
そうでない部分について整理してみましょう。
基本的には食べられない理由
うすいえんどうの皮(さや)は
硬さがあり食感もよくないため、
一般的には食べられないとされています。
料理に使うときは必ず皮を取り除き、
中の豆だけを調理するのが基本です。
グリンピースとの違いはここにあり、グリンピースもうすいえんどうも同じ「えんどう豆」ですが、食べ方のルールは少し異なるのです。
| 豆の種類 | 皮(さや)の扱い |
|---|---|
| うすいえんどう | 硬いため基本的に食べない |
| スナップえんどう | さやごと食べられる |
| グリンピース | さやは食べず、中の豆だけを使用 |
皮を使ったレシピや工夫があるケース
一方で、
最近は皮をそのまま捨てずに工夫するレシピも紹介されています。
たとえば、
じゃがいもや玉ねぎと一緒に煮込んで
ミキサーにかけると、
ポタージュ風のスープに仕上げることができます。
皮そのものは固いため食感は残りますが、
煮込んで攪拌することで
口当たりがやわらかくなり、
料理に活かせるのです。
基本は豆だけを食べるけれど、工夫次第で皮も楽しめるというのが、うすいえんどうの面白いところといえるでしょう。
うすいえんどうの正しい剥き方と保存方法
うすいえんどうは
調理の前に皮を剥く必要があります。
実はこの作業、
ちょっとしたコツを知っているとぐっと楽になります。
ここでは、
初心者でもできる簡単な剥き方と、
剥いた後の扱い方をまとめます。
初心者でもできる簡単な皮の剥き方
うすいえんどうの皮剥きは意外と簡単で、
次の手順でスムーズに進められます。
手が汚れにくい作業なので、お子さんと一緒に楽しむのもおすすめです。
| 手順 | ポイント |
|---|---|
| ① さやの両端を確認 | 湾曲した側を上にして持つと剥きやすい |
| ② 先端を軽く押す | 皮がパカッと左右に開く |
| ③ 豆を指で押し出す | 粒がつぶれないようにやさしく取り出す |
剥いた後の保存方法(冷蔵・冷凍のポイント)
剥いた豆は時間が経つと
表面が乾きやすいため、
できるだけ早めに調理するのが理想です。
もしすぐに使わない場合は、
乾燥を防ぐようにラップや袋で密閉して冷蔵庫へ。
数日以内に使えないときは、冷凍しておくと便利です。
冷凍する場合は
空気をしっかり抜いて袋に入れると、
使うときに豆の状態がきれいに保たれます。
調理直前に剥くと豆のふっくら感が長持ちするので、ここもポイントです。
うすいえんどうのおいしい食べ方
うすいえんどうはやさしい甘みが特徴で、
いろいろな料理に活用できます。
豆の風味を生かした和風の定番から、
ちょっと工夫した洋風のアレンジまで
楽しめるのが魅力です。
ここでは、
代表的な食べ方をいくつか紹介します。
王道の豆ごはんで旬を味わう
関西では春の定番料理
として親しまれているのが「豆ごはん」です。
炊きあがったご飯に剥いた豆を混ぜることで、
豆のツヤと香りがそのまま楽しめます。
塩味を控えめにすることで、うすいえんどう本来の甘みを感じやすくなるのがポイントです。
| 豆ごはんのポイント | おすすめ理由 |
|---|---|
| ご飯に後から混ぜる | 豆の色や風味が損なわれにくい |
| 塩加減は控えめ | 豆の自然な甘さを引き立てる |
副菜やおつまみにおすすめの洋風アレンジ
うすいえんどうは
洋風の味付けとも相性が良く、
軽くつぶして調味料と和えると
食感が楽しい一皿になります。
例えば、
ベーコンと炒めて
「ジャーマンえんどう」にすると、
豆の甘みと塩気がバランスよく引き立ちます。
黒こしょうをたっぷり加えると大人向けの風味に仕上がるので、夕食の副菜にぴったりです。
皮を捨てずに活用できるポタージュレシピ
通常は捨ててしまう皮ですが、
じゃがいもや玉ねぎと一緒に
煮込んでミキサーにかければ、
やさしい緑色のポタージュに変身します。
皮の繊維がやや残るので、
気になる場合は
こして仕上げると滑らかになります。
豆と皮の両方を使うことで、うすいえんどうをまるごと楽しめるのが魅力です。
うすいえんどうをもっと楽しむための豆知識
うすいえんどうは調理法だけでなく、
ちょっとした知識を知っておくと
選び方や楽しみ方が広がります。
ここでは、
買うときに役立つポイントや
家庭で取り入れやすい豆知識をまとめます。
スーパーで新鮮な豆を選ぶコツ
うすいえんどうは
皮付きで売られていることが多く、
見た目で鮮度をある程度判断できます。
さやの色が鮮やかで、ハリがあるものを選ぶのが基本です。
さやにシワが寄っていたり、
色が黄色っぽくなっているものは
収穫から時間が経っているサインです。
| 状態 | 鮮度の目安 |
|---|---|
| さやがピンと張っている | 新鮮で豆の甘みが強い |
| さやにシワがある | 収穫から時間が経過している |
| 色がくすんでいる | 鮮度が落ちている可能性が高い |
うすいえんどうを食卓で楽しむ工夫
うすいえんどうは
豆ごはんや炒め物だけでなく、
スープやサラダにもアレンジできます。
また、
見た目の鮮やかな緑色を活かすと、
料理全体が彩り豊かになります。
料理の仕上げにトッピング感覚で加えるだけでも食卓が華やぐので、使い方を工夫してみましょう。
旬の時期にたくさん買って、家庭の定番レシピに加えておくと便利です。
まとめ|うすいえんどうを無駄なく美味しく楽しもう
ここまで、
うすいえんどうの特徴や皮の扱い方、
おすすめの食べ方について紹介してきました。
春ならではの食材として人気の理由は、
ふっくらとした豆の甘みと優しい香りにあります。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 皮は食べられる? | 基本的には食べず、中の豆だけを調理する |
| 調理のコツ | 直前に皮を剥くと豆がしっとり仕上がる |
| 食べ方の例 | 豆ごはん、洋風アレンジ、ポタージュ |
うすいえんどうは、皮を工夫して活用すれば無駄なく楽しめる食材です。
旬の時期に手に入れたら、
ぜひ豆ごはんやスープなど、
いろいろな料理に取り入れてみてください。
「皮は食べられるの?」という疑問から広がる楽しみ方があるのも、この豆の面白さです。